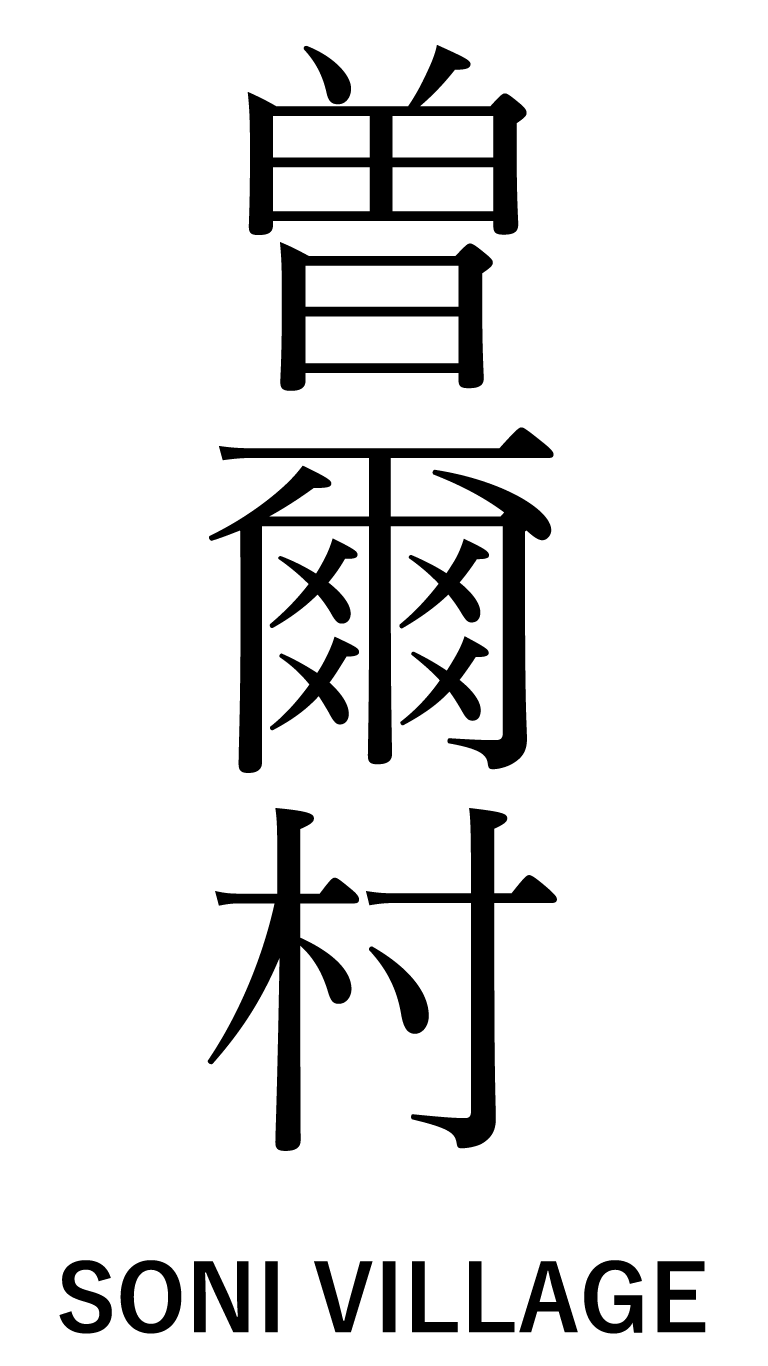「子供をのびのび育てたい」トマト農家・料理人2つの顔を持つ一家のパパ
標高400~500mという高原地帯に位置する曽爾村の寒暖差を活かして、1年のなかでも夏から秋の間だけ作られる「曽爾高原トマト」。
曽爾のトマト作りを担っていくトマト農家の後継者になるべく、2021年に地域おこし協力隊として移住してきた鬼塚幸太朗さんは、今年の春に協力隊を卒業しました。
晴れてトマト農家として独立した傍ら、鬼塚さんは村内に『DRIVE IN ONIYUPOS』(以下、「オニユポス」)という飲食店をこの夏にオープン。
オニユポスは、それぞれ独自の強みや経験を持った3人の若者がチームを組んで生まれた、アメリカンスタイルの飲食店。
お店の定番人気メニューであるハンバーガーには、鬼塚さん自らが育てたトマトと、規格外のトマトを利活用したBBQソースが使用されています。
トマト農家と飲食店の料理人という、2足のわらじを履く鬼塚さんとは、一体どんな人なのか?彼自身とその家族の、曽爾での暮らし・仕事について迫ります。
都会を離れ、田舎で子育てをしたいと考えている方、曽爾村での就農を考えている方、是非ご覧ください。
子供のために、料理人から農家へ

──移住してトマト農家になる前は料理を専門にお仕事をされていたんですか?
「そうですね。以前はアメリカンレストランで有名な『Hard Rock Cafe』の京都店に勤務していて、料理人歴は10年程度でした。『Hard Rock Cafe』は飲食店だけでなくケータリング事業も展開していたんですけど、東京オリンピックが開催予定だった2020年に、オリンピックのケータリング人員として東京へ異動になったんです。そのタイミングで同じ職場だった現在の奥さんと結婚しました。」
──鬼塚さんが地域おこし協力隊になられたのは2021年ですから…2020年の東京異動から約1年で曽爾村に移住したことになりますね。何があったのでしょうか?
「東京に異動してから第一子が生まれたんですけど、移住のきっかけは子育てと自分の身体のためです。飲食業はずっと立ちっぱなしだし、厳しい世界だし、日の出前に出社して、日没後に帰宅するという、太陽を浴びない生活リズムが続いたりもしていたので、身体に悪いという意識もあったのですが、それ以上に、仕事が忙しすぎて生まれたばかりの子供と向き合う時間が取れなかったんですよね。
子供の成長を健康な身体で見守っていきたい。太陽を浴びて空気が綺麗なところで仕事がしたい。新鮮な物を食べたい…。そんなことを考えていた矢先に、世の中がコロナでパンデミックになったので、いっそのこと夫婦の出身地である関西に戻って生活し直したいなって。子育てと、自身の働き方と、コロナと、色々重なって今に至ります。」
──トマト農家になろうと思ったきっかけは?
「料理人のスキルを活かしてできることは何かと考えた際、農家を思い浮かべたんです。
それで、何の食物で農家になろうかって考えたとき、丸齧りしても美味しいし、火を通しても別の美味しさがあり、いろんな料理で活躍するトマトを思いついて。トマト農家について調べまくっていたら、曽爾村がトマト農家の地域おこし協力隊を募集されていて、すぐに現地開催の説明会に申し込みました。」
──トマト農家を目指して、いざ足を踏み入れた曽爾村はいかがでしたか?
「東京から電車とバスをたくさん乗り継いで、ようやく曽爾に降り立ったときに吸って浴びた新鮮な空気。あれは忘れられへん…。その瞬間に、『やれるかどうかではなく、ここでやりたい』という気持ちが固まりました。説明会ではトマト農家のことや、仕事のしんどさ、厳しい現状等、色んなことを教えてもらいましたが、曽爾へのトキメキは抑えられず(笑)。東京へ帰った瞬間に妻に曽爾村移住をプレゼンしました。」
──奥さんはどんな反応でしたか?
「そもそも、飲食店に勤務していた頃から農家は気になっていた職業だったのですが、『農家=親から引き継ぐもの』と思っていたんです。初期投資もかかるし、ノウハウもないので、結局は憧れで終わっていたんですよね。でも曽爾村の協力隊では様々な補助やトマト部会での研修が充実していて、当初イメージしていたよりハードルがぐんと下がったんです。
そんな安心材料もあり、『子供と向き合う時間を作るために』という前提で移住と農家になりたい旨を妻に相談したら、妻も仕事と子育ての時間の使い方に同じような課題を感じていたので、『良いの見つけてきたね』って、受け入れてくれました。」
──実際に曽爾村に移住してからの奥さんの反応は?
「同じ関西出身でも、僕は学生時代に車やバイクで曽爾には来たことがあったんですよ。当時は『SONYが作った村なんかな』とかふざけたこと考えてましたけど(笑)。
一方、妻は曽爾に行ったことが無かったので、単純に『関西に帰る』という感覚でいたらしいんです。けど実際に来てみたら『想像以上に山奥やん…』って驚いていましたね。(笑)」
「のびのび子育て」の醍醐味を実感する環境

──生まれたばかりの子を連れての曽爾移住でしたが、今ではお子さんも増えて5人家族ですよね?
「移住した年に生まれた子が今年4歳で、移住して1年後に生まれた2人目が2歳。そして移住4年目の今年に3人目が生まれました。あのまま東京に住んでいたら、子供は1人で終わっていただろうなぁと感じます。」
──移住が子供の人数にも関係しているんですか?
「そうですね。結婚した当初から夫婦で漠然と『子供は3人欲しいね』って話していたんですが、都会だと仕事に追われて子育てに参加できない点が一番課題だし、保育園の待機児童問題や、3人の子供がのびのび育つほど大きい家を持つのも難しく、『3人欲しい』という夫婦の理想に、知らぬ間にブレーキがかかっていたんです。でも、曽爾みたいな田舎暮らしは都会のようにブレーキを踏む要素が少ないので、理想としていた3人の子供を授かることができました。」
──曽爾の保育園にお子さんを預けてみて感じることは?
「曽爾の保育園、めっちゃ良いですよ。まず保育料も給食費も無料なのはとてもありがたいし、あとは保育園の環境も最高ですね。あたり一面が自然に囲まれた環境下で、自然や地域の人・文化に触れさせてもらえるカリキュラムが多いんです。親子料理教室など、親子で楽しめる行事もありますしね。」
──都市部では待機児童問題がありますが、曽爾の児童数は少ないですよね。
「各クラスで10名前後の少人数なんですけど、少人数だからこそ先生たちもしっかり成長を見守ってくれていて、『一人で階段登れるようになった』『今日はこんなことをしていた』って細かいことを共有してくれるんです。まるでわが子のように教育してくれるので安心して預けられますね。」
──保育園以外の環境でも子育てに良い点を感じることはありますか?
「近所の人から近所じゃない人まで、みんなで子供を可愛がってくれる村です。子供が生まれたときは「抱っこさせてね」って近所のおばちゃんにも言ってもらえたり、知らん人が喋りかけてきて子供にお菓子買ってくれたり。血は繋がっていなくても、みんながおじいちゃんおばあちゃんなんですよ。そんな人がたくさん居てくれるから、子供も大人に対して警戒心を持っていないし、社交的に育っているな~と感じますね。
もしかしたら、これが古き良き子育ての形なのかな。妻も、曽爾に移住しなかったら子供3人おらんかったし、都会から移住してきてよかった、と思ってくれています。」
──都会だと子供3人に見合う家を持つのも難しいと仰っていましたが、移住してからの住環境はどうでしょうか?
「古民家に住みたいという欲も特になく、ただただ広い家に住みたかったんですけど、要望を満たす古民家がタイミングよく空き家バンクで見つかったんです。はじめは賃貸で借りて、数年経ったところで購入させてもらいました。
古民家の広い座敷は子供がのびのびできるし、集合住宅じゃないから、子供たちがキャッキャッ騒いでも周りに迷惑がかかりにくいですね。お隣さんがいても敷地が広くて隣接はしていないので。逆に、実家に帰って家の中で騒いでいたらおばあちゃんに叱られて『なんで家で騒いだらあかんのやろ?』って不思議そうな顔してる。そういう子供の姿を見ていたら、曽爾でのびのび育ってくれてるんやなぁ…ってしみじみ実感します。」
──「最初は賃貸で、暮らしに慣れてからお家を購入」という流れは多くの移住希望者さんが憧れるスタイルですが、どのような流れでそうできたのでしょうか。
「あ、鬼塚家は実は最初から、賃貸ではなく購入の方が良かったんです…(笑)
ですが、いきなり売買契約ができないという当時の空き家バンクの体制(※)や、協力隊の制度的にも活動費の中から家賃補助が出るということで、3年後に購入させてもらいたい旨を大家さんに相談したうえで、協力隊任期期間中は賃貸にしていました。
3年間支払っていた家賃の合計金額を差し引いてお家を購入させてもらえるかな~と思っていましたが、結局、家財道具の整理や家の補修などで大家さんが色々とお金をかけてやってくださったので、家賃で払っていた分を差し引くとかそういった小細工はなしに、大家さんの希望価格で購入させてもらいました。」
(※:現在は空き家バンクの運営体制が変わり、当時の状況とは異なります)
自分にしかできない農家と料理人の二面性

──今年の春に協力隊を卒業されましたが、トマト農家としてのお仕事は実際にやってみていかがですか?
「大変なのは覚悟してたし、楽な仕事ではないことも頭では理解いていましたが、予想通り大変ですね。毎年気候も土壌環境も変わるし、農業ってセオリーがないんだ…って。
協力隊卒業直前の3年目からは、ハウス16棟分を自身で管理し始めたんですが、めっちゃ大変で…。16棟って結構な量なんですけど、『頑張るぞ!』っていう初期衝動で、つい(笑)
もちろん最初の勢いや直感は大事にすべきだ、という想いもあるんですけど、それでも多すぎたと反省しました。ただ、協力隊の間にその壁に当たれたので、計画的に今後を考えるきっかけにはなりましたけどね。」
──協力隊任期中にBBQソースも商品化しましたよね?
「3年目に規格外トマトを使ったBBQソースも開発・商品化しました。『TOMATO AND PEACE!』という屋号をつけて、トマト作りの傍らパッケージもデザインしたりしましたね。色々試行錯誤しながらやって大変に感じることはもちろん多いですが、景色も空気も良い曽爾の屋外だと、どれだけ疲れていても頑張れる。贅沢な環境だと思います。」


──独立から半年経ちますが、調子はいかがですか。
「卒業後の独立に向けて色々調整しながら一念発起しようとしたところ、協力隊最終日に生死をさまよう病に倒れてしまい、そこから2ケ月10日の入院生活を過ごしたんです。
しばらく意識を失っていたのですが、トマトはもちろん、それ以外の仕事にも追われていた時期だったので、目覚めた瞬間に『仕事せなやばいから、はよ帰らせてくれ』と言ってしまって、ICUで看護士さんに怒られました。家族のことはもちろん、曽爾に移住してまで始めたこの仕事だったからこそ、『はよ元気になって帰って仕事せな』という意識が強くて…。逆に、だからこそ命の糸が切れずに繋がったのかなと思います。」
──入院生活中、トマトの畑はどうしていたのでしょうか。
「若手からベテランの農家さんまで、みんなが集まって僕の畑作業を手伝ってくれていたんです。誰かが『TOMATO AND PEACE!』のグループLINEも作ってくれて、そこにみんなが作業を手伝ってくれている様子を写真で送ってくれたんですよね。…みんながアベンジャーズに見えてくるんですよ。曽爾のアベンジャーズ(笑)。彼らの姿が病と闘う励みになりました。
退院して村に帰ってきてからも、『僕のことって、村内放送されたんかな?広報誌に掲載されたんかな?』って思うくらい、色んな人から声をかけてもらって、中には泣いて安心してくれる人もいて、曽爾の人って温かいんやな、帰ってこれて良かったって実感しました。」
──家族のように心配してくれていたんですね。
…それにしても、ICUで看護士に叱られてしまうほどに追われていた仕事って、トマト以外にも何かしていたのでしょうか?
「オニユポスのオープンに向けた準備ですね。オニユポスをオープンする前から、料理人だった経験を活かして、村内外のイベントにフード出店することも多くあったんです。そこで、村内イベントで出店仲間として親しくなった仲間3人で、オニユポスをオープンしようって話になったんです。
病に倒れた時がちょうどオープン前のタイミングだったので、自分自身が手を動かしたり、準備に参加できないもどかしさは感じていましたが、その分仲間と村民さんが頑張ってくれている姿を見て、『早く元気になって帰らなあかん』って、モチベーションに繋がりました。」
そこから、医師や看護師さんも信じられない驚異的な回復力を見せたそうです。
──お店は2024年9月に正式オープンとなりましたが、トマト農家と料理人との両立で気を付けていることはありますか?
「『トマト農家なのに飲食店やるんか?』とか、そういうご意見ももしかしたらあるかもしれないですが、そういったご意見って良いか悪いか本人には直接届かないんすよね…(笑)。でも、そう不安に思われないように、あくまで『トマト農家がベースなんだ』という意識は変わっていないし、それは忘れたらあかん大切な軸だと思ってやっています。
トマト栽培は、幸い1年間ずっと忙しい訳ではないんです。春~秋の時期は畑に付きっきりになりますが、ハウスの片づけが終わった後の冬は閑散期で、トマトだけの稼ぎでは生きていくのが難しい分、春夏秋冬を通してトマト農家と料理人の自分のバランスをうまく取っていきたいです。
有難いことに妻の両親も近くに越してきたので、子育てと仕事の両方がおざなりにならないように、今後は家族皆で協力し合いながらやっていきたいと考えています。」
──まさに半農半Xを体現されていると感じますが、大変さは感じませんか?
「もちろん大変です。村民さんからも『無理しやんときや』ってたくさん言ってもらえますが、今の仕事が楽しいんですよね。自分が作ったトマトとBBQソースがハンバーガーになり、お客さんの口に入り、美味しい!って言ってもらえて…。
美味しい料理を作っても、美味しいトマトを作っても、誰かに食べてもらえる瞬間って生産者も料理人もなかなか見られないですが、僕は見れてしまうんですよ。農業をやりながら飲食業もやらせてもらっているからこそ見られる景色。こんなに楽しいことはないです。
農業も飲食業も、どんな仕事も楽ではないと思っているので、その覚悟は持っています。でも、自分が本当にやりたいことだったら、多少厳しかろうが楽しめるはずなんです。」


慣れれば「ふつう」な曽爾暮らし
──2024年は協力隊卒業・闘病・開業など、鬼塚さんにとってまさに節目の年だったと思いますが、あらためて、これまでを振り返って感じる「曽爾暮らし」とは?
「子育てしやすい環境だったり、仕事もチャレンジし甲斐がある環境だったり、色んな要素がありますが、一般的な暮らしの視点だと、思っていたよりも曽爾での暮らしは難しくないですね。車で行こうと思ったらどこでも行けるし。『浄化槽』とか『草刈り』とか、最初は慣れないこともたくさんありましたけど、耐え難いほどのことではなかったです。難しく思っていることがあったとしても、慣れちゃえば「ふつう」のことなんです。
星は美しいし、空気も綺麗やし、緑がカラフルやし…。あ、『緑って色んな色があるんやな』と曽爾に来て本当に思ったんですよ(笑)。慣れなくて大変だと思っていたことも、都会と違って自然環境が良いことも、トータルで慣れれば「ふつう」なんです。…失ったものは、家からすぐ近くのコンビニくらいかな!(笑)」
取材中、どこかしらにクスっと笑えるユーモアを織り交ぜてくる鬼塚さん。
家族5人で暮らしていくこと、トマト農家と料理人の2足のわらじを履くこと、病に伏してもあきらめずに踏ん張ったこと…。大変なことだらけの人生でも、曽爾の地でユーモアを忘れず、「楽しくやってこうよ」という哲学が彼の中にあるように感じました。
皆さん、そんな鬼塚さんが作ったトマト・BBQソース・ハンバーガーを是非食べてみてくださいね。
おしまい
(2024年11月取材)